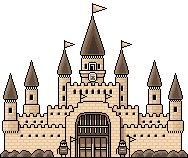<ぶらり草津>
関ヶ原の戦いで勝利を収めた、徳川家康が慶長6年(1601)に
交通・運輸の便宜を図るために街道の整備を始めました。
東海道を上方と江戸とを結ぶ最も重要な街道として位置づけ、
宿駅ごとに人馬を常置させ、公文書や荷物を次の宿駅へと輸送する伝馬制度をいち早く制定し、
翌慶長7年には中山道にも伝馬制度を定めました。
そして寛永12年(1635)に徳川家光によって参勤交代が制度化され、
街道と宿場の通行が、より活発化していくようになりました。
「五街道」の呼称が使われ始めたのは、道中奉行が万治2年(1659)に設置され、
管轄下となった街道の名称を略したことによっています。
その5つは「東海道」「中山道」「日光道中」「奥州道中」「甲州道中」になります。
この五街道は、全て江戸の日本橋が起点となり、各方面へと道が伸びてゆきます。
<草津宿>
東海道五十三次のうち、江戸より数えて52番目の宿場町で、
東海道と中山道が分岐・合流している交通の要衝でした。
天保14年(1843)の「宿村大概帳」によると草津宿には、
田中七左衛門本陣と田中九蔵本陣の2軒の本陣、2軒の脇本陣、72軒の旅籠がありました。
(脇本陣、旅籠の数は時代によって変化します)
また、草津宿は中山道と東海道の分岐点で、その分かれ目に追分道標が立っています。
|

追分道標 |
道標の上部にある現在の火袋は木製ですが、
文政4年(1821)頃につくられた
「栗太志」によると、
当時は銅製であったと記されており、
大変立派なものであったことが分かります。 |

草津宿本陣 |
「本陣」とは本来、
戦の際に軍の総大将のいる本営
のことを指していました。
 
式台を持った玄関 と 上段の間 |

立木神社 |
1200余年の歴史を有する、
滋賀県隋一の古社。

通安全厄除けの神社 |

うばがもちや |
永禄十二年、織田信長に滅ぼされた
佐々木義賢一族の遺児を託された
乳母が養育のために売ったのが始まり
と云われています。
 |